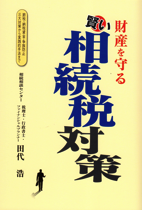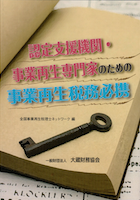決算・税務申告・節税・相続のことなら、千葉県千葉市の田代会計事務所にお任せください。
平成5年開業の豊富な経験と高い技術
〒260-0004 千葉市中央区東本町7−2
記事は掲載当時の税法に基づいております
043-224-3618
営業時間 | 9:00~17:30(土日祝を除く) |
|---|
お気軽にお問合せください
相続税の節税対策
誰でも、今日からできる「簡単」相続税節税対策
税理士のうちでも、相続税を得意とする税理士は限られています。 相続税とは、死亡した人の財産を、相続、遺贈、死因贈与により取得した人に係る税金です。
贈与税は相続税の補完税といわれています。相続税を免れるために生前贈与をされては、相続税の意味がなくなってしまいます。それを補うために、贈与税は、相続税に比べて課税最低限や税率などが、厳しく税負担が重くなっています。

相続税対策は、遺産分割対策と、納税資金対策と、相続税の節税対策の順に行います。ひとつの対策を実行することにより、3つの目的を同時に実現できる一石三鳥の対策です。税理士の腕の見せ所です。
1. 財産の現況と構成をつかむ
預貯金、土地(貸地)、家屋(貸家)、上場株式等有価証券など、プラスの財産と、住宅ローン、未払金などのマイナスの財産、これらの財産を一覧表にまとめ、1年に1回は財産目録を作成することをお奨めします。
それによって、財産の評価額の増減もわかります。土地家屋等の不動産が、財産全体の中でどのくらいの割合を占めているかを把握することは大切です。不動産 は、すぐに換金し難いものです。相続税の納税は、金銭一時納付が原則です。物納の場合も、要件がそろわないと物納不適格ということになってしまいます。
2. 法定相続人を増やす
孫や相続人の配偶者等と養子縁組することにより、相続人の人数が増えれば、相続税の遺産に係る基礎控除額も増額し、課税遺産総額を法定相続人の数で除して求める、法定相続分に応ずる取得金額は減額しますので、相続税の総額が減り、節税対策になります。

ただし、実子がある場合は、相続税法上カウントされる相続人は1人までです。実子がいない場合は2人です。 他の相続人の相続分が減少することによるトラブルや、孫が養子になることによる弊害もありますので、メリットデメリットをよく検討する必要があります。
他の相続人の相続分が減少することによるトラブルや、孫が養子になることによる弊害もありますので、メリットデメリットをよく検討する必要があります。
3. 生前贈与により相続財産を減らす
暦年課税による贈与の場合、毎年110万円まで基礎控除があるので、その範囲内の贈与であれば、贈与税が課税されずに、財産を異動させることができます。
110万円の贈与でも、5人にすれば550万円、それを10年に続ければ5,500万円も相続財産を減らすことができます。

連年贈与については特に問題ないという意見もありますが、毎年同額を同時期に贈与をし、10年に渡ってするなどというメモまで残してあると、連年贈与と認定され、110万円×5年=550万円に贈与税が課税される恐れがあるため、金額や贈与時期を変える方が無難です。贈与契約書を作成しておきましょう。
民法(549条)に規定する贈与は、自己の財産を無償で相手方に与える意思を示し、相手方がそれに受諾することによって成り立つ片務・諾成・無償の契約で す。あげる人「贈与者」ともらう人「受贈者」の「あげます」「もらいます」明確な意思のやりとりが必要です。一方的にあげたことにしたり、自分で通帳を管 理したり引き出しをしたりしていると、いくら贈与税の申告をしていても、贈与と認められませんので注意してください。贈与税対策は税理士に必ず相談しま しょう。
贈与税には、相続時精算課税という制度もあります。一度こちらを選択すると110万円の基礎控除のある暦年課税制度には戻れませんので、この点も注意してください。
また、相続開始前3年以内にされた贈与財産は、相続財産に加算されます。この場合課税された贈与税額は控除されます。つまり、亡くなってしまうかもしれな いという間際になって、バタバタと生前贈与対策をしたものは無しにして、相続税の計算をするということです。相続人ではない息子の嫁や孫への贈与は、これ に該当しませんので、当時の贈与税で完結しています。
4. 贈与税の配偶者控除を使う
適用要件に合えば、その年の課税価格から、次のうち少ない方の金額を控除できます。
- 2,000万円
- 贈与を受けた居住用不動産の金額と
贈与を受けた金銭で居住用不動産に充てた部分の合計額
◆ 要 件
- 同じ配偶者からの贈与税の配偶者控除の適用は、1回のみ
- 婚姻期間が20年以上(1年未満切捨)である配偶者間の贈与であること
- 贈与財産は、居住用不動産か、居住用不動産取得のための金銭であること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた居住用不動産、贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、居住し、その後引き続き居住の見込みであること
- 一定の書類を添付して、贈与税の申告をすること
5. 財産の評価額を下げる
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
相続や遺贈によって宅地等を取得した個人で、居住用や事業用に使われていた宅地等で一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものがある場合には、納税義務の選択により、その宅地等の評価額の一定割合を減額する特例があります。
● 対象宅地
- 特定事業用宅地等
- 特定居住用宅地等
- 特定同族会社事業用宅地等
- 貸付事業用宅地等
● 限度面積
- 特定事業用等宅地等(特定同族会社事業用宅地等を含む)…400平方メートル
- 特定居住用宅地等…330平方メートル
- 貸付事業用宅地等…200平方メートル
- 対象宅地を合わせて使う場合は次の式で換算します
- 特定事業用等宅地等を選択する場合又は特定居住用宅地等を選択する場合
特定事業用等宅地等 ≦400 であること。
であること。
また、特定居住用宅地等 ≦330 であること。
であること。 - 貸付事業用宅地等及びそれ以外の宅地等を選択する場合
特定事業用等宅地等×200/400
+特定居住用宅地等×200/330
+貸付事業用宅地等 ≦200 であること。
であること。
- 特定事業用等宅地等を選択する場合又は特定居住用宅地等を選択する場合
● 減額割合
- 特定事業用宅地等…80%
- 特定居住用宅地等…80%
- 特定同族会社事業用宅地等…80%
- 貸付事業用宅地等…50%
● 分割要件
特例の適用を受けようとする宅地等が相続税の申告期限までに分割されていること。
ただし、分割されていない場合であっても、次のいずれかに該当するときは、この特例の適用を受けられます。
- 相続税の申告期限から3年以内に分割された場合
- 相続税の申告期限から3年を経過する日において分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたとき
● 申告要件
相続税の申告書に、この特例を受けようとする旨などを記載するとともに、一定の書類を添付する必要があります。
アパートの建築による貸家建付地の評価減
貸地のように評価額が高く、現金化し難い土地を生前に処分する
6. 非課税枠を利用する
保険金の非課税限度額
被相続人の死亡により相続人(相続を放棄した者を除く)が取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していた場合、す べての相続人が受け取った保険金の合計額が非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象とみなされます。
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
- 法定相続人の数は、相続の放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
- 養子がいるときは、法定相続人に含む養子の数が変わります。被相続人に実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人です。
なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。
退職手当金等の非課税限度額
被相続人の死亡により、退職手当金等を遺族が受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもので、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象とみなされます。
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
- 法定相続人の数は、相続の放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
- 養子がいるときは、法定相続人に含む養子の数が変わります。被相続人に実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人です。
なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。
相続税対策は、田代税理士事務所へご相談ください。
お問合せはこちら
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。無料相談実施中です!

お気軽にお問合せください
心無い同業者による当ホームページ(リニューアル前)の無断転載がありました。
ホームページを閲覧の際には、お気をつけください。 当ホームページ無断転載厳禁
当ホームページ無断転載厳禁
お問合せはこちら
代表者紹介
事務所案内
著書・執筆記事