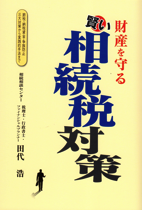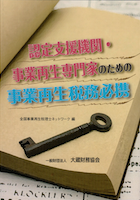決算・税務申告・節税・相続のことなら、千葉県千葉市の田代会計事務所にお任せください。
平成5年開業の豊富な経験と高い技術
〒260-0004 千葉市中央区東本町7−2
記事は掲載当時の税法に基づいております
043-224-3618
営業時間 | 9:00~17:30(土日祝を除く) |
|---|
お気軽にお問合せください
グループ法人税制

千葉の当税理士事務所のお客様も多く該当し、注意が必要な税制です。少人数で会社経営をされている方や親子・夫婦で株式等を保有されているなど、連結納税制度とは違い、極めて一般的な同族法人間どうしでもグループ法人税制は適用される場合があります。
グループ法人税制は、ごく普通の中小零細企業でも頻繁に適用がありますので注意してください。この点、小規模法人ではめったに適用がない連結納税とは大きく違うところです。
平成22年税制改正で導入された、グループ法人税制について、連結納税制度(平成14年)が選択適用であるため、同じように考え、中小零細企業ではあまり関係が無いと考えている経営者の方も多いように感じられます。
しかし、資本金の大きい小さいに関係なく、一定の要件のもと、グループ法人税制は、強制適用されるため注意が必要です。 100%子法人を有する親法人だけでなく、個人が複数の会社の株を100%保有している場合にも適用されます。
グループ法人税制の適用範囲
税法上では、完全支配関係について、
「一の者が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係又は一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係」
「一の者」が個人である場合には、その者と特殊の関係にある次の者も含めて完全支配関係を判定する。
1) 株主等の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)
2) 株主等と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者
3) 株主等の使用人
4) 上記1)~3)以外の者で、株主等から受ける金銭等によって生計を維持している者
5) 上記2)~4)に掲げる者と生計を一にするこれらの親族
とされています。
税理士と経営者が協力して、親子兄弟等の親族の株式保有関係を洗い出し、グループ法人税制の適用範囲を明確にする必要があります。
100%グループ法人間の受取配当
100%グループ法人間の資産の移転
100%グループ法人間の寄付金
100%グループ法人間の資本関連取引
について、取扱いが異なるので注意する必要があります。税理士が誤りがないかをチェックすべきポイントと考えられます。
グループ法人単体課税制度と連結納税制度との違い
- 運用については、グループ法人単体課税制度(以下「グループ法人」)は強制適用であるのに対し、連結納税制度(以下「連結納税」)は選択制となっています。
- グループの範囲としては、グループ法人は一の者(法人・個人)とその100%支配会社(完全支配関係)が範囲であるのに対し、連結納税は親会社とその100%子会社(完全支払関係)が範囲です。
- グループ内の各社の所得通算は、グループ法人は所得通算しないのに対し、連結納税は所得を通算します。連結法人の場合、欠損法人があれば連結所得は減少されます。
- グループ内の一定規模の資産の譲渡損益は、どちらも当該資産のグループ(連結グループ)外への移転等の際まで計上を繰り延べます。
- グループ内の寄付は、どちらも寄付金の支出側は損金不算入、受手側は益金不算入(受手側は課税所得が減少)と処理します。
- 受取配当金益金不算入における負債利子は、どちらも負債利子控除は不要(課税所得は減少)とされます。
- 中小法人特例の適用について、どちらも適用できないこととなっています。
中小企業向け特例措置の大法人の100%子会社に対する適用は、平成22年4月1日以後開始する事業年度から適用です。
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人に係る次の制度については、資本金の額若しくは出資金の額が5億円以上の法人又は相互会社等の100%子法人には適用しないこととします。
- 中小企業者等の法人税の軽減税率
- 特定同族会社の特別税率(留保金課税)の不適用
- 貸倒引当金の法定繰入率
- 交際費等の損金不算入制度における定額控除制度
- 欠損金の繰戻しによる還付制度
グループ法人税制における100%グループ等の判定
100%グループ等の判定を行う場合において完全支配関係がその判定の基礎になります。この場合、一の者が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係、又は一の者との間に当事者間の完全支配関係がある法人相互の関係と考えられます。
「一の者」とは、法人・個人が特定されていないことから「法人」、「個人」のいずれも判定の核となり、また法人についてはその種別、所在地等による区分がないことから、内国法人による支配関係、外国法人による支配関係及び個人による支配関係が対象となります。また、当事者の他方に含まれる法人は、株式会社(特例有限会社を含む)、持分会社(合名、合資、合同の各会社)、協同組合等のほか、医療法人も含まれます。
完全支配関係の判定においては、自己株式を除いた発行済株式総数のうち、使用人が組合員になっている従業員持株会が保有する株式及び役員等がストックオプションにより取得した株式を合わせた割合が5%未満の株式が除かれます。
100%グループ内の法人間の一定の資産の譲渡取引等
100%グループ内の法人間の一定の資産の譲渡取引等に伴う譲渡利益、損失については、グループ外へ移転されるまで認識されない制度です。この制度は平成22年10月1日以後に行う譲渡損益調整資産について適用されます。
連結法人間取引の損益の調整制度を変更し、内国法人が譲渡損益調整資産をその内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人に譲渡した場合には、その譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額を、所得の金額の計算上、その資産のそのグループ外への移転等の時に、その移転を行った法人において計上する制度とされました。
譲渡損益調整資産
譲渡損益調整資産とは、次に掲げる資産でその帳簿価額が1,000万円以上の資産をいいます。
- 固定資産
- 棚卸資産である土地(土地の上に存する権利を含む)
- 有価証券(売買目的有価証券を除く)
- 金銭債権
- 繰延資産
なお、この譲渡損益の繰延制度は、完全支配関係にある内国法人間の取引を対象としていることから、個人及び外国法人との間で行った資産の移転には適用はありません。
譲渡損益の実現
譲受法人による譲渡、償却、評価換え、貸倒れ、除却等があった場合の損益の調整
内国法人が上記の適用を受けた場合において、その譲渡を受けた法人(譲受法人)おいて次に掲げる事由が生じたときは、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額は、当該内国法人の各事業年度(一定の事業年度を除く)の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入されます。
- 譲渡損益調整資産の譲渡、償却、評価換え、貸倒れ、除却等
- 内国法人が譲渡損益調整資産に係る譲受法人との間に完全支配関係を有しないこととなった場合
- 連結納税制度の適用開始に伴い連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益の適用がある場合
100%グループ内の法人間の寄附
平成22年10月1日以後に支出する寄付金の額及び同日以後に受ける受贈益の額について適用されます。
【損金不算入と益金不算入】
法人による完全支配関係がある内国法人間の寄附金について、支出法人において全額損金不算入するとともに、受領法人において全額益金不算入とされ、その益金不算入とされる金額は受領した法人の利益積立金に加算されます。
- 完全支配関係がある内国法人間の寄附金について、寄附金を支出した法人において全額損金不算入とされ、これを受領した法人において全額益金不算入とされ、その益金不算入とされる金額を受領した法人の利益積立金額に加算されます。(法人による支配関係に限る)
- 内国法人間の寄附金については、寄附金を支出した法人において寄附金限度額内で損金算入され、これを受領した法人において全額益金算入されます。
この場合の寄附金は、いわばグループ内における資金の移動とみることができることから、支出法人及び受領法人ともに課税除外とします。法人間の寄附を対象とすることから個人(同族関係者を含む)により完全支配されている法人間の寄附金については適用されません。
100%グループ内の法人からの受取配当金の益金不算入
完全子法人株式等(※1)に係る受取配当金等について、負債利子控除をしません。
※1
完全子法人株式等とは、配当等の額の計算期間(前回の配当等の額の基準日の翌日(※2)から今回の配当等の額の基準日までの期間)中、継続して完全支配関係があった他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く)の株式又は出資です。
※2 次の調整が有ります。
- 前回配当基準日が1年以上前又は1年以上前に設立された法人からの初回配当 → 1年前の日の翌日
- 1年以内に設立された法人からの初回配当 → 設立日
- 1年以内に取得した新規発行株式についての初回配当 → 取得日
平成22年4月1日以後開始する事業年度の所得に対する法人税について適用され、同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については従前通りです。
なお、平成22年4月1日以後に開始する事業年度において支払いを受けた配当等の額について、その計算期間が同日前に開始していた場合であっても、計算期間と通じてその配当等の額を支払う他の内国法人との間に完全支配関係があれば、完全子法人株式等に係る配当等の額として、新制度が適用されます。詳細は税理士にご確認ください。
完全支配関係にある子法人の解散に伴う親法人の処理
(1) 子会社株式の処理
- 親法人が完全支配関係にある子法人の解散に伴う残余財産の分配により金銭その他の資産の交付を受けた場合、又は子法人の株式を有しないこととなった場合(残余財産の分配を受けないことが確定した場合を含む)には、その子法人株式の譲渡損益の計算上、譲渡対価の額は譲渡原価の額に相当する金額として、譲渡損益を計上しません。
- 子法人に係る損失の額に相当する金額は、親法人において資本金等の額を減額します。
平成22年10月1日以後の解散について適用します。
(2) 子会社の未処理欠損金の引継ぎ
- 完全支配関係にある子法人の残余財産が確定した場合において、その子法人に未処理欠損金額があるときのその未処理欠損金額は、親法人の欠損金額とみなして、繰越控除が適用されます。
未処理欠損金とは、残余財産の確定の日の翌日前7年以内に開始した各事業年度において生じた欠損金(繰越控除または繰戻還付の基礎となった金額を除く)をいいます。
なお、支配関係が5年以内に生じている場合には、未処理欠損金の引継ぎが制限されます。
お問合せはこちら
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。無料相談実施中です!

お気軽にお問合せください
心無い同業者による当ホームページ(リニューアル前)の無断転載がありました。
ホームページを閲覧の際には、お気をつけください。 当ホームページ無断転載厳禁
当ホームページ無断転載厳禁
お問合せはこちら
代表者紹介
事務所案内
著書・執筆記事