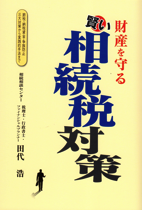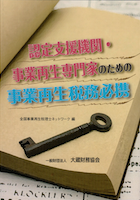決算・税務申告・節税・相続のことなら、千葉県千葉市の田代会計事務所にお任せください。
平成5年開業の豊富な経験と高い技術
〒260-0004 千葉市中央区東本町7−2
記事は掲載当時の税法に基づいております
043-224-3618
営業時間 | 9:00~17:30(土日祝を除く) |
|---|
お気軽にお問合せください
相続税の債務控除
相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産があります。プラスの財産にばかり目が行きがちですが、マイナスの財産も漏れがないように計上することも大切です。
相続税の債務控除の対象者と範囲
無制限納税義務者
相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る)により財産を取得した者が居住無制限納税義務者又は非居住無制限納税義務者である場合においては、その相続又は遺贈により取得した財産については、課税価格に算入すべき価格は、その財産の価格から次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額になります。
- 被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む)
- 被相続人に係る葬式費用
制限納税義務者
相続又は遺贈により財産を取得した者が制限納税義務者である場合においては、その相続又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるものについては、課税価格に算入すべき価格は、その財産の価格から被相続人の債務で次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額になります。
- その財産に係る公租公課
- その財産を目的とする留置権、特別の先取特権、質権又は抵当権で担保される債務
- 上記1,2を除くほか、その財産の取得、維持又は管理のために生じた債務
- その財産に関する贈与の義務
- 被相続人が死亡の際この法律の施行地に営業所又は事業所を有していた場合においては、その営業所又は事業所に係る営業上又は事業場の債務
非課税財産の債務
下記1及び2の非課税財産の取得、維持、又は管理のために生じた債務</b></font>の金額は、債務控除の規定による控除金額に算入しません。
- 墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの
- 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが相続又は遺贈により取得した財産でその公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
ただし、2については、その者がその財産を取得した日から2年を経過した日において、なおその財産をその公益を目的とする事業の用に供していない場合に、その財産の価額を、課税価格に算入する規定により、財産の価額を課税価格に算入した場合においては、控除金額に算入します。
控除すべき債務
控除すべき債務
債務控除の規定によりその金額を控除すべき債務は、確実と認められるものに限ります。
債務控除の規定によりその金額を控除すべき公租公課の金額は被相続人の死亡の際債務の確定しているものの金額のほか、被相続人に係る所得税、相続税、贈与税、登録免許税、自動車重量税、消費税、酒税、たばこ税、印紙税その他の公租公課の額で政令で定めるものをみます。
確実な債務
債務が確実であるかどうかについては、必ずしも書面の証拠があることを必要としません。
なお、債務の金額が確定していなくてもその債務の存在が確実と認められるものについては、相続開始時の現況によって>確実と認められる範囲の金額だけを控除するものとします。
控除すべき債務の注意点
公租公課の異動の場合
課税価格又は相続税額の申告、更正又は決定があった後、債務控除の規定により控除すべき公租公課に異動が生じたときは、その課税価格及び相続税額について、更正を要するので注意が必要です。
保証債務
保証債務については控除しません。
ただし、主たる債務者が弁済不能の状態にあるため、保証債務者がその債務を履行しなければならない場合で、かつ、主たる債務者に求償して返還を受ける見込みがない場合には、主たる債務者が弁済不能の金額は、その保証債務者の債務として控除します。
連帯債務
連帯債務については、連帯債務者のうちで債務控除を受けようとする者の負担すべき金額が明らかになっている場合には、その負担金額を控除し、連帯債務者のうちに弁済不能の状態にある者(弁済不能者)があり、かつ、求償して弁済を受ける見込みがなく、その弁済不能者の負担部分をも負担しなければならないと認められる場合には、その負担しなければならないと認められる部分の金額もその債務控除を受けようとする者の負担部分として控除します。
消滅時効の完成した債務
相続の開始の時において、既に消滅時効の完成した債務は債務控除の控除すべき債務に規定する確実と認められる債務に該当しないものとして取り扱うものとします。
相続時精算課税適用者の死亡により承継した
相続税の納税に係る義務の債務控除
特定贈与者の死亡以前その特定贈与者に係る相続時精算課税適用者が死亡したことから 相続時精算課税に係る相続税の納税義務の承継等の規定によりその相続時精算課税適用者の相続人(包括受贈者を含み、その特定贈与者を除く)が、相続時精算課税適用者の有していた相続時精算課税の適用を受けていたことに伴う納税に係る権利若しくは義務を承継した場合において、
又は贈与者の死亡前に相続時精算課税選択届出書を提出しないで受贈者が死亡したことから、その受贈者の相続人(包括受贈者を含み、その贈与者を除く)がその受贈者の有することとなる相続時精算課税の適用を受けることに伴う納税に係る権利若しくは義務を承継した場合において、
その承継した納税に係る義務は、その相続時精算課税適用者又はその受贈者の死亡に係るその相続時精算課税適用者の相続人又はその受贈者の相続人の相続税の課税価格の計算上、債務控除の対象とすることはできないので注意が必要です。
相続財産に関する費用
民法885条「相続財産に関する費用」の規定により相続財産の中から支弁する相続財産に関する費用は、債務控除の規定に掲げる債務とはならないので注意が必要です。
その者の負担に属する部分の金額の意義
債務控除に規定にする「その者の負担に属する部分の金額」とは、
相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る)によって財産を取得した者が実際に負担する金額をいいます。
この場合において、これらの者の実際に負担する金額が確定していないときは、民法の法定相続分又は包括遺贈の割合に応じて負担する金額をいうものとして取り扱います。
ただし、共同相続人又は包括受遺者がその相続分又は包括遺贈の割合に応じて負担することとした場合の金額が相続又は遺贈により取得した財産の価額を超えることとなる場合において、その超える部分の金額を、他の共同相続人又は包括受遺者の相続税の課税価格の計算上控除することとして申告があったときは、これを認めます。
葬式費用
葬式費用となるもの
債務控除の規定により葬式費用として控除する金額は、次に掲げる金額の範囲内のものとします。
- 葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において、埋葬、火葬、納骨又は遺がい若しくは遺骨の回送その他に要した費用
(仮葬式と本葬式とを行うものにあっては、その両者の費用) - 葬式に際し、施与した金品で被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用(お布施)
- 1又は2に掲げるもののほか、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの
- 死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用
<具体例>
- お通夜、告別式(仮葬儀、本葬儀を含む)にかかった費用
- 葬儀に係る飲食代
- 火葬、埋葬、納骨に係る費用
- 火葬場までの交通費
- 運転手さんへの心付け
- 遺体の搬入費用
- お布施、戒名、読経に係る費用
- お寺さん等への御車料
- 喪主、施主負担分の生花、盛りかご等の費用
- 近所のお手伝いさん等へのお礼
- その他、通常葬儀に伴う費用
葬式費用とならないもの
次に掲げるような費用は、葬式費用として取り扱わないものとします。
- 香典返礼費用(社会通念上相当な香典収入は所得税の非課税)
- 墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料(仏具、位牌等、非課税財産となるもの)
- 法会に要する費用(初七日、四十九日等)
- 医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用
※ 墓碑の買入代金
被相続人の生存中に墓碑を買い入れ、その代金が未払であるような場合には、その未払代金は債務として控除しないので注意が必要です。
<具体例>
- 香典返し
- 生花、盛りかご等の費用(喪主、施主負担分は除く)
- 位牌、仏壇、墓石、墓地等の費用
- 初七日、四十九日等法会に係る費用
- その他、通常の葬儀に伴わない費用
相続を放棄した者の債務控除
相続を放棄した者及び相続権を失った者については、債務控除の規定の適用はありません。
しかし、その者が現実に被相続人の葬式費用を負担した場合においては、その負担額は、その者の遺贈によって取得した財産の価格から債務控除しても差し支えありません。
お問合せはこちら
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。無料相談実施中です!

お気軽にお問合せください
心無い同業者による当ホームページ(リニューアル前)の無断転載がありました。
ホームページを閲覧の際には、お気をつけください。 当ホームページ無断転載厳禁
当ホームページ無断転載厳禁
お問合せはこちら
代表者紹介
事務所案内
著書・執筆記事