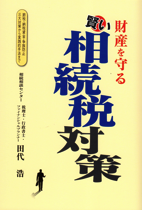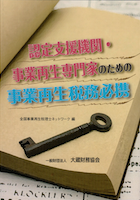決算・税務申告・節税・相続のことなら、千葉県千葉市の田代会計事務所にお任せください。
平成5年開業の豊富な経験と高い技術
〒260-0004 千葉市中央区東本町7−2
記事は掲載当時の税法に基づいております
043-224-3618
営業時間 | 9:00~17:30(土日祝を除く) |
|---|
お気軽にお問合せください
税理士からの節税アドバイス 減価償却費
減価償却費は節税や税務調査対策上、注意を要する科目のひとつです。会社の費用のうち大きな割合を占める費用の一つで、損益にあたえる影響も大きいため、税務調査に際して減価償却費に対しては重点的に行われます。
減価償却費とは
減価償却費とは、固定資産の取得価額を、その使用可能期間にわたって一定の計算方法により各事業年度に配分し、収益と対応させるための手続きです。
使用により固定資産の価値が減少した分だけ費用とするのは現実的には困難であるため、減価償却費の計算は見積もりの計算となります。
したがって、資産の種類ごとに法定耐用年数が定められ、その法定耐用年数の間に定額法や定率法等の方法によって償却額を計算しなければなりません。減価償却を行う固定資産を減価償却資産と呼びます。
税理士からの決算に際してのアドバイス
決算にあたっては、減価償却資産について再度見直しをして減価償却費の計算を誤らないようにしましょう。特に期中に取得したものについては、法定耐用年数や償却方法等、取得後はじめの決算での処理が翌期以降に引き継がれるので特に注意が必要です。
- 期中に取得した資産はきちんと計上されているか。
- 取得価額に誤りはないか。(取得価額に含める付随費用等)
- 法定耐用年数は合っているか。
- 償却方法は税法上採用することが可能な方法か。
- 期中に取得の場合は月割の計算をしているか。
- 期中の除却、売却の処理にもれはないか。
などになります。
税理士がアドバイスする償却方法の選択
減価償却費の計算にあたり、選択できる償却方法はいくつかあります。一般的によく選択されているのは定額法と定率法です。
定額法は減価償却費の額が毎期均等になるように取得価額に償却率を乗じて計算する方法です。
定率法は毎期一定の償却率を未償却残高(取得価額ー既償却額)に乗じて計算する方法です。
定率法では当初の減価償却費が大きく、後半になるにつれ減価償却費が小さくなっていきます。
法人税法ではそれぞれの資産ごとに選択できる償却方法が決まっています。(平成19年4月1日以後取得の場合)
- 建物・・・定額法
- 建物以外の有形減価償却資産.・・・定額法、定率法
- 無形減価償却資産・・・定額法
建物以外の有形減価償却資産は定額法か定率法を選択できますが、どちらを選択するかは税務署に届出を出さなければなりません。
届出を出さなかった場合には、定率法で計算することになります。したがって、建物以外の有形減価償却資産について定額法を選択したいという場合は、定額法を選択する旨の届出を忘れずに出す必要があります。
減価償却についてご不明な点やご相談があれば、千葉市の税理士、千葉市中央区の田代税理士事務所へお問い合わせください。
減価償却の対象資産
減価償却の対象となる資産か対象とならない資産かは、税務調査においても争点になることが多く注意が必要です。
対象となるのは有形固定資産または無形固定資産のうち、時の経過や使用することによってその価値が減少していくもので、事業の用に供しているものです。
具体的には、建物や構築物、機械及び装置、車両及び運搬具、器具備品などです。
棚卸資産、有価証券、繰延資産となるものは対象となりません。
また、土地も使用や保有期間によって資産価値が減少するものではないため対象となりません。
したがって、土地付き建物を取得した場合等には、その土地と建物の取得価額を正確に区別して計上する必要があります。土地の取得価額の一部又は全部が建物として計上されてしまっては、建物の減価償却費として費用となる金額が大きくなってしまうからです。
稼働休止資産の注意点
減価償却の対象にならないものとして、もうひとつ注意が必要なものは稼働休止資産です。
稼働を休止しているものは、事業の用に供されていないため減価償却の対象とはなりません。ただ、休止期間中でも必要な維持補修が行われていて、いつでも使用できる状態になっているものは減価償却の対象となります。
税務調査では、稼働休止中であるがいつでも使用できる状態である、というのを証明できるかがポイントとなりますので、裏付けの資料をきちんと整備しておくとよいでしょう。
有姿除却の注意点
使用を止め、今後通常の方法で事業の用に供する可能性がない固定資産については、廃棄をしていない場合であっても、有姿除却として除却の処理をすることができます。
例えば、ある製品の製造を廃止したことにより、その製品製造用の機械を今後使用する見込みがなく、他の製品の製造にも使用することが出来ないものだが、処分するには費用がかかるのでそのまま残しておく場合などが該当します。
有姿除却を計上した場合に税務調査で争点となるのは、今後確実に事業の用に供することがないのか、という点になります。税務調査対策にはこれを立証できるような書類を用意しておくことが必要です。
固定資産の取得価額
何をもって減価償却資産の取得価額とするかというのは、その後の減価償却費の計算にも影響を与えるため、税務調査においても注目される項目です。
減価償却資産の取得価額とすべきものの基本的な考え方は、購入代価及び付随費用等で、その資産を事業の用に供するまでにかかる費用の合計額です。
ただし、付随費用のうち取得価額に含めないことができるとされているものがあります。
借入金利子や不動産取得税、自動車取得税などです。「取得価額に含めないことができる」とは、取得価額に含めても良いし、含めなくても良いし、どちらかを選んでも差支えないということです。
取得価額に含めて処理をすれば、法定耐用年数にわたって減価償却により損金となりますが、含めなければ取得した事業年度の損金となります。したがって、 「取得価額に含めないことができる」ものをきちんと把握し、取得した事業年度の損金として処理することが節税のポイントとなります。
節税になる減価償却資産の取得
業績が好調で利益が多く出ているときに、固定資産の購入を考える経営者の方もいらっしゃると思います。
取得価額が比較的少額の固定資産の場合には、通常の減価償却とは異なり、損金算入額が大きくなる方法を選択出来るものがあり節税につながります。
- 10万円未満又は使用可能期間が1年未満・・・事業の用に供した事業年度に全額損金経理をした場合は全額損金算入が可能です。
- 20万円未満・・・20万円未満のもののうち一部または全部を一括して償却する方法を選択した場合、その合計額×その事業年度の月数/36 で計算した金額が、損金算入の限度額となります。
- 30万円未満・・・青色申告書を提出する中小企業者等は、その取得価額が30万円未満のものについて全額損金経理をした場合には、確定申告書に明 細書の添付を要件として、全額損金に算入されます。この場合は取得価額の合計額が300万円を超えるときは、300万円に達するまでの金額が限度になりま す。(租税特別措置法規定のため期限付き)
このように、青色申告書を提出する中小企業者等であれば、30万円未満のものは全額損金にできるため、固定資産を購入するときにはこれらの要件を念頭に検討されると効果的に節税できるでしょう。
税理士が推奨する否認されないための書類保存
税務調査で否認されないためには、固定資産を購入したときの請求書や領収書の保存についても注意が必要です。
「取得価額に含めないことができる」ものを取得時に損金としている場合には、支払額の記載された領収書だけではなく、何を取得価額として何を含めなかったのかが明確に分かるような書類も保存しておかなければなりません。
また、一括償却資産や30万円未満の特例が適用されるような資産については、金額要件を満たしていなければ適用できないため、一単位あたりの金額が分かるような書類が必要でしょう。
節税になる中古資産の取得
中古で取得した固定資産については、減価償却費の計算をする際に法定耐用年数によらないため注意が必要です。中古資産を取得後にあと何年使用できるのかを 合理的に見積もることができれば、その見積耐用年数を基礎に減価償却を計算します。実際は残存耐用年数を合理的に見積もることが困難な場合も多く、その場 合は簡便法によって計算します。 簡便法では残存耐用年数を以下のように計算します。
- 法定耐用年数の一部を経過したもの
法定耐用年数-経過年数+(経過年数×20%)または法定耐用年数×20% - 法定耐用年数の全部を経過したもの
法定耐用年数×20%
中古で取得した資産は、新品のものより使用できる期間は短くなるのが普通ですから、それを見積りにも反映させて法定耐用年数よりも短い期間で償却できるこ とになります。短い期間で償却できるということは、一度に償却費として損金に計上できる金額が大きくなることを意味します。
実際の資産の耐久性等は考慮に入れず償却費の額だけをみるのであれば、同じ取得価額の 新品と中古の資産では、中古のものを購入したほうがその期に計上できる損金の額が大きくなるため、節税という意味では良いでしょう。
中古資産に関する資料保存
中古資産を取得して簡便法により見積耐用年数を計算する場合には、購入した時点での経過年数により見積耐用年数が変わり減価償却費の額が変わりますから、その経過年数を証明できるような書類を保存しておく必要があります。
車であれば車検証に初年度登録日が記載されていますし、その他の資産であれば製造年月等が分かるような書類があることが望ましいです。
また、中古資産にその資産の価値を高めたり、耐用年数を伸ばしたりする資本的支出を行った場合については、簡便法を適用できず法定耐用年数で計算しなければならない場合もありますので注意が必要です。
中古資産の減価償却についての注意点
中古資産を取得して使用を開始した場合は、簡便法による見積耐用年数によって減価償却を行うことができます。
しかし、この耐用年数の見積もりは事業の用に供した事業年度にのみ行うことができるので注意が必要です。
事業の用に供した事業年度に法定耐用年数で計算した場合には、その翌事業年度以降で見積耐用年数に変更することはできません。
お問合せはこちら
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。無料相談実施中です!

お気軽にお問合せください
心無い同業者による当ホームページ(リニューアル前)の無断転載がありました。
ホームページを閲覧の際には、お気をつけください。 当ホームページ無断転載厳禁
当ホームページ無断転載厳禁
お問合せはこちら
代表者紹介
事務所案内
著書・執筆記事