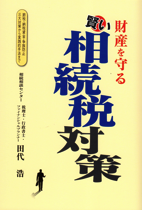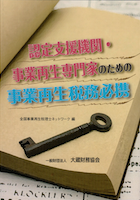決算・税務申告・節税・相続のことなら、千葉県千葉市の田代会計事務所にお任せください。
平成5年開業の豊富な経験と高い技術
〒260-0004 千葉市中央区東本町7−2
記事は掲載当時の税法に基づいております
043-224-3618
営業時間 | 9:00~17:30(土日祝を除く) |
|---|
お気軽にお問合せください
銀行借入れ 融資 相談
銀行の融資
銀行は融資に際して企業を格付し、格付に応じて融資条件を変えています。格付は定量評価と定性評価に対して行われます。
従来から、大手メガバンクでは、定量評価(財務諸表のよる格付)を重視してきましたが、地方銀行や信用金庫等も含めて、今ではすべての金融機関で定性評価よりも定量評価の比重が高まっています。
- 定量評価とは → 財務分析による数字的な評価項目
- 安全性 流動比率、自己資本比率、固定長期適合率、ギアリング比率
- 収益性 総資本経常利益率、売上高経常利益率、収益フロー
- 成長 売上高、自己資本額、経常利益増加率
- 返済能力 債務償還年数、キャッシュフロー額、インタレスト・ガバレッジ・レシオ
この中でも金融機関は融資に対して、安全性の各指標と、返済能力の指標を重視しています。
- 定性評価とは → 経営環境や経営能力といった企業の質的な評価項目。各金融機関担当者による主観的要素が加味されます。
- 遡明資料(証拠資料)が求められる
- 市場動向 景気感応度 市場規模 競合状態 業歴 経営者・経営方針 株主 従業員のモラル 営業基盤 競争力 シェア
田代会計事務所の所長は、国の認定機関である千葉県再生支援協議会で、専門プロジェクトリーダーとして銀行の支店長とともに、財務改善のコンサルティングや大蔵財務協会が事務局をしている全国事業再生税理士ネットワークの幹事を経験しています。このような実務経験を通じて、銀行が有利な条件でも貸付したい会社と、銀行の協力が得られない会社との違いについて、ご相談、ご説明をいたします。
銀行借入 融資条件を有利にするためのポイント
銀行は担保があれば融資をしたいという時代はとっくに終わっています。担保物を処分する手間や手続きを考えれば当然です。 銀行は自分たちにとって、将来良いよいお客様になる企業(個人)か否か、貸した金は金利とともに本業の利益の中からスムーズに回収できるかを判断基準にしています。
税務署提出用の決算書、節税対策のみの決算書では片手落ちです。銀行対策をも考慮した決算書の作成が求められています。税務署提出用と銀行用の決算書を別々に作成することは犯罪行為ですから絶対にやめましょう。粉飾決算書も同様です。
銀行によっても異なりますが、正常先を7区分~13区分し、それぞれのランクによって融資条件を変えています。正常先だからといって安心できません。 優良企業は益々有利な条件で融資が受けられます。 正常先の中でも上のランクに入るための方法や、決算書のポイントについても相談いたします。
過去の業績数値に基づいた信用格付のランクと、資金の使い道と、返済の財源が明らかになっているかがポイントです。担保、金利や保証人が総合勘案されて融資条件が決まります。
銀行借入の実例
同じ業種で同じように今期損失が出たA会社とB会社。 A会社ではスムーズに融資が受けられたのに、B社では借入ができなかった。この違いは何でしょうか。
同じく、業種や業歴、売上の規模、利益はほとんどかわらないC社とD社。 C社の融資金利は1%を切っているのに、D社は3%の金利を金融機関から求められた。この違いはどこにあるのでしょうか。
会社を設立して、1年未満でもあるにもかかわらず、日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫)から借入が出来た会社と、自己資金500万円があるのに借入を拒否された会社。その原因は何でしょうか。
銀行借入のポイントを知っているか知らないかで、長い経営を行っていくうえでどれだけの差になるかわかりません。 決算書で同じ利益を出していても、評価される会社と評価されない会社の違いは何でしょうか。
メインバンクとサブバンクの付き合い方の違いがわかっていますか?
メインバンク、サブバンク等を銀行はこだわります。これらをごっちゃにして借入等を行うと後々メインバンクの協力が得られなくなることがあります。融資シェアのバランスはどのようにとれば良いのか?
個人と法人融資を受けやすいのはどちらか?
自己資金が無いと本当に融資はされないのか?
銀行から、不当に不利な条件を突き付けられた場合の対処法は?
銀行のモニタリング機能をうまく活用し、有利な条件で借入をするために必ず定期的に実行しなければならないことは何か?
減価償却をしないで利益を計上した決算書を銀行はどのように審査するのか?
銀行が融資に際して自己資本を重視する理由は何か?
銀行に提出された決算書をそのまま活用しているわけではありません。
実態修正はどのような勘定科目に対してどのように行われているのか?
銀行の格付(正常先、要注意先、破綻懸念先、実質破産先、破綻先)の格付ランクはどうすれば上がるのか?
経営改善に向けた取り組みを高く評価してもらうためにすべきことは何か?
銀行から嫌われることをすれば、その時は有利になっても長い目で見たら不利になる場合もあります。 銀行が企業に最もしてほしくないことは何か?
銀行からスムーズに融資を実行してもらうための方法
1. 中小企業金融円滑化法(モラトリアム法)を上手に活用
2009年12月4日施行された金融機関に返済猶予などの条件変更の義務を課すものです。
2011年3月までの時限立法になっています。これらの法をうまく活用すれば返済猶予が可能です。合わせて金融検査マニュアル(中小企業融資編)が改訂されました。
ただし、本業での利益を上げる業務の改善がなければ、単に、延命等にすぎなくなりますので、実現可能な経営改善計画書の作成と実行が必要です。
2. キャッシュ・フロー計算書の作成
キャッシュ・フロー計算書は、貸借対照表、損益計算書と同格の大切な財務諸表として位置づけることが必要です。 キャッシュ・フロー計算書を作成していない場合、格付を下げる金融機関もあります。キャッシュ・フロー計算書は当たり前の財務諸表と考え、決算毎に(毎月)作成することは今や常識です。
3. 制度融資の上手な活用方法
制度融資には、低金利のものや固定金利のものがあります。
創業資金を調達できる制度もありますのでこれらの制度をうまく活用することが大切です。
利子補給や、信用保証料の補助が受けられる制度もあります。
これらの制度融資を上手に使って資金調達をする方法についても相談いたします。
有利な借入、融資をスムーズに行うためのポイントから、金融機関から評価される決算書作成の重要事項、メインバンク、サブバンクとの付き合い方や、いざとなった時に銀行から協力を得ることができる日頃のポイントまで、融資、借入、資金繰り、経営改善計画書の書き方まで、税理士、融資コンサルタントが無料相談をいたします。お気軽に御相談下さい。
お問合せはこちら
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。無料相談実施中です!

お気軽にお問合せください
心無い同業者による当ホームページ(リニューアル前)の無断転載がありました。
ホームページを閲覧の際には、お気をつけください。 当ホームページ無断転載厳禁
当ホームページ無断転載厳禁
お問合せはこちら
代表者紹介
事務所案内
著書・執筆記事